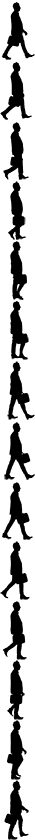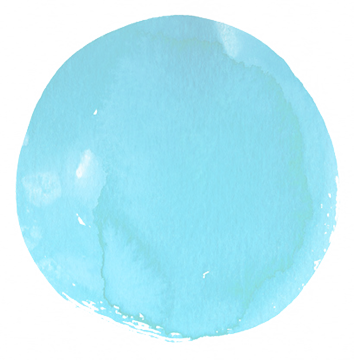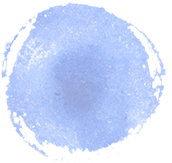Topics
2025年度(令和7年度)の労務関連法改正について
2025.02.02労務管理
2025年4月から2026年3月の法改正事項の一覧を公開させて頂きます。
本年度は育児介護休業法及び雇用保険が改正施行されることから、就業規則(主に育児介護休業規程)の改定、雇用保険の給付申請、育児・介護対象労働者への制度周知等の実務面での影響が大きくございます。
その他労務管理に関する諸法令も多く改正されますのでご留意ください。
2025年度(令和7年度)人事労務関連法改正事項一覧
※ それぞの概要をクリックすると、関連リンクが開きます。
| 法律名 | 概要 | 内容 | 施行時期 |
|---|---|---|---|
| 安全衛生法 | 労働者死傷病報告等の報告事項の電子申請の義務化 |
労働者死傷病報告の他、下記の報告が電子申請が義務化 ・定期健康診断 ・心理的な負担の程度を把握するための検査 ・衛生管理者、産業医選任報告等 |
2025年1月1日 |
| 事業者が行う退避や立入禁止等の措置の労働者の保護措置の義務化 |
・危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲 を作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大 ・危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化 |
2025年4月1日 | |
| 熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を義務化(予定) |
・熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、異常を早期に発見するための体制を整備し、関係者に周知しなければならない。 ・熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止等症状の重篤化を防ぐために必要な措置等をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならない。 |
2025年6月1日 | |
| 雇用保険法 |
(育児休業等給付関連) 出生後休業支援給付の創設 |
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業等を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで100%相当となるよう)を支給。 | 2025年4月1日 |
|
(育児休業等給付関連) 育児時短就業給付の創設 |
2歳未満の子を養育する被保険者が、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給 | 2025年4月1日 | |
|
(育児休業等給付関連) 育児休業給付金の延長手続き |
保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められたことが必要。 育児休業給付延長時は、従来の入所不承諾通知に加えて、「延長事由認定申告書」及び「保育所等の利用申込書(写)」が必要となる。 |
2025年4月1日 | |
| 自己都合離職者の給付制限の見直し |
原則の給付制限期間を2月間→1ヵ月間へ短縮する。 ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付 制限期間を3ヶ月とする。 |
2025年4月1日 | |
| 暫定措置の延長 |
・雇止めによる離職者(特定理由離職者)の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付を2年間延長 ・教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の80%から60%に引き下げた上で2年間延長 |
2025年4月1日 | |
| 就業促進手当の見直し | 就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる | 2025年4月1日 | |
| 教育訓練休暇給付金の創設 | 5年以上の被保険者期間のある雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇(無給)を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を 支給する教育訓練休暇給付金を創設 | 2025年10月1日 | |
| 高年齢雇用継続給付の給付率 | 60歳時点の賃金額と60歳以降の給与額が75%未満となった際に受給できる高年齢雇用継続給付について15%の給付率→10%に変更。 | 2025年4月1日 | |
| 厚生年金保険法 | 高年齢雇用継続給付金の給付率引き下げに伴う老齢年金の調整率の変更 | 高年齢雇用継続給付の最大給付率が10%に引き下げられ(改正前は15%)、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の4%に相当する額に引き下げられる(改正前は6%)ことに伴い、当該調整率の逓減率について、必要な改正を行うもの。 | 2025年4月1日 |
| 育児介護休業法 | 子の看護休暇の見直し |
・対象となる子の範囲の拡大(小学校3年生修了まで) ・取得理由の拡大(感染症に伴う学級閉鎖等) ・労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満適用除外規定の撤廃 ・名称の変更(子の看護等休暇) |
2025年4月1日 |
| 所定外労働の制限(対象拡大) | 請求可能となる労働者の範囲を、3歳未満の子から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大 | 2025年4月1日 | |
| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | 業務の性質上、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務について、短時間勤務に代替する措置としてテレワークを追加 | 2025年4月1日 | |
| 育児のためのテレワーク導入 | 3歳未満の子を養育する者労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、努力義務化 | 2025年4月1日 | |
| 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | 公表義務の対象となる企業を従業員数1,000人超から従業員数300人超の企業に拡大(「両立支援のひろば」等) | 2025年4月1日 | |
| 介護休暇を取得できる労働者の緩和 | 労使協定による継続雇用期間6カ月未満適用除外規定の撤廃 | 2025年4月1日 | |
| 介護離職防止のための雇用環境整備 |
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、下記いずれかの措置を講ずることを義務化。 ①研修の実施 ②相談窓口の設置 ③事例の収集・提供 ④利用促進に関する方針の周知 |
2025年4月1日 | |
| 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 |
介護に直面した旨の労働者に対して、下記内容を個別に実施しなけばならない。 ・周知事項(制度の内容、申出先、給付金に関すること) ・周知・意向確認の方法(面談、書面交付、Fax、電子メール等) また、介護に直面する早い段階(40歳時)に介護休業制度等の情報提供を行うことを義務付け |
2025年4月1日 | |
| 介護のためのテレワーク導入 | 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、努力義務化 | 2025年4月1日 | |
| 柔軟な働き方を実現するための措置 |
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、下記5つのうち、2つ以上の措置を選択して講ずる必要がある。 (過半数労働者代表等からの意見聴取必須) ①始業時刻等の変更(時差勤務・フレックス) ②テレワーク(10日以上/月) ③保育施設の設置運営等 ④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 ⑤短時間勤務制度 |
2025年10月1日 | |
| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 |
①妊娠・出産の申出時 ②子が3歳になるまでの時期に下記内容を個別に聴取しなければならない。 ・聴取内容(勤務時間、勤務地、業務量等) ・聴取方法(面談、書面交付、Fax、電子メール等) また、聴取した内容により、仕事と育児の両立について、自社の状況に応じて配慮しなければならない。 |
2025年10月1日 | |
| 障害者雇用促進法 | 障害者雇用調整金、報奨金の変更 | 法定雇用率を超過した場合に支給される調整金・報奨金は令和6年度の実績に基づく令和7年度の支給から、調整金は対象人数が10名を超える場合には1人当たり29,000円→23,000円へ、報奨金は対象人数が35名を超える場合は1人当たり21,000円→16,000円へ減額されます。 | 2025年4月1日 |
| 法定雇用率の算定における除外率の見直し |
除外率設定業種の除外率を100分の10ずつ引き下げることとなった。 対象業種一例:建設業、鉄鋼業20%→10%へ |
2025年4月1日 | |
| 障害者雇用状況を報告義務範囲の見直し | 雇用状況報告の対象である事業主の範囲について、対象労働者数43.5人→37.5人へ変更。 | 2024年4月1日 | |
| 職業安定法 | 職業紹介事業者の紹介手数料率の実績公開義務化 |
紹介手数料率の実績公開と違約金規約の明示の義務化 「人材サービス総合サイト」に掲載 |
2025年4月1日 |
| 高年齢者雇用安定法 | 高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了 | 定年後65歳までの「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止 | 2025年4月1日 |
| 次世代育成支援対策推進法 | 有効期限の延長 | (時限立法のため)令和7年3月31日までの期間を令和17年3月31日まで10年間の期間延長。 | 2025年4月1日 |
| 育児休業取得に関する状況把握・数値目標の義務付け |
常時雇用する労働者の数が100名超の企業に対し、 ①計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等 ②育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定。 |
2025年4月1日 | |
| 事業主の責務の追加 |
多様な労働条件の整備として、 育児休業を取得しやすい職場環境の形成及び労働時間の短縮の取組を条文に追加。 |
2025年4月1日 | |
| 税法(主に所得税) | 令和7年分基礎控除・給与所得控除の引上げ、特定親族特別控除(仮称) |
(1)基礎控除 基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。 (2)給与所得控除 給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。 (3)特定親族特別控除(仮称) ※(3)については、2026年1月1日より適用 |
2025年1月1日 |